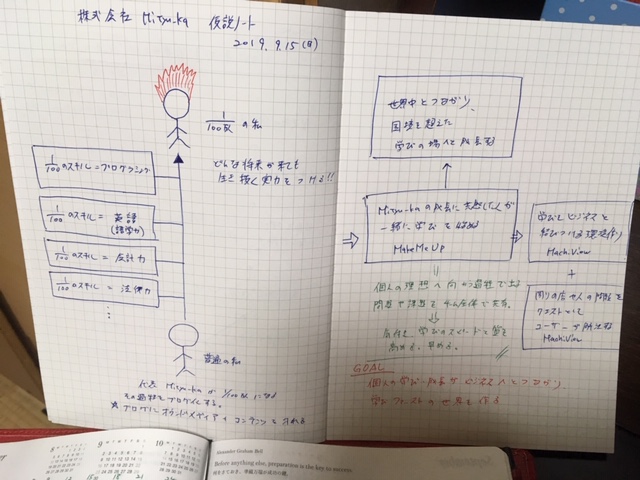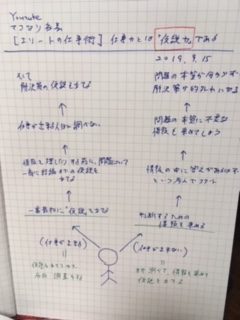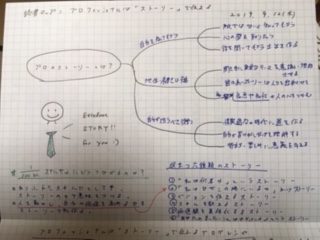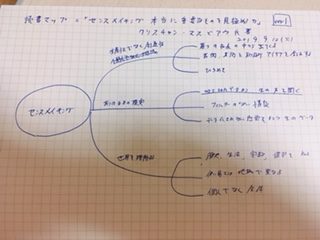前回の記事~ダメサラリーマンからの脱却 ver1 で、
私のダメポイントをさらけ出しました。
「確認しない。人に聞けない」
けれど、ダメポイントを自覚してからといって、
すぐに聞けるようになった訳じゃないんです。
当たり前ですよね。
自分の欠点ってそう簡単に治せないから困るんですから。
じゃあ、どうしたか?
「雑談をする」
自分の考えや行動を上司などにさっと報告出来ない理由は単純。
「お前はこんな事も分からないのか!」とか、
「聞く内容を間違っていたらどうしよう…」とか、
間違いや失敗を極度に怖がっているからです。
そして、そんな時は間違いなく自信がありません。
私のように確認しない&聞けない人の特徴として、
コミュニケーション下手です。私は凄く苦手でした。
何を考えているか分からない相手と話すことが苦手です。
だから、「雑談をする」のです。
仕事の話だと、お互い緊張感を持って対応しますよね。
私のように話すことが苦手だと、さらに緊張感がアップ。
手に汗べったりです(笑)
この緊張感は相手にも伝わります。
私が相手の考えが分からないように、相手も私の考えが分からないのです。
すると、お互い(特に相手)が会話の細部まで神経を張り巡らして
ミスを許さない空気が出来上がってきます。
緊張感を下げて、相手との話し易さのハードルを下げる方法が雑談にあるのです。
「1つの雑談が、仕事のやり易さに繋がる」
多くの方が仕事は複数の人でしていますよね。
あなたが会社のトップでも、平社員でも、中間管理職でも
お客さんがいて、業者がいて、金融機関がいて。
何かしらの形で人と接している。
仕事は一筋縄でいかないことが多いはずです。
自分1人では解決できない問題も、周りの方の力を借りればアッサリと解決!
そんな場面があるはずです。
じゃあ、何がキッカケで周りの方の力を借りられたのか?
話し易い関係です。
仕事の成果って、実は能力の差じゃなくてコミュニケーション力の差じゃないかと思います。
「聞けない」のではなくて、聞けない雰囲気を作ってしまっている。
周りの人を動かす力と言えるかもしれないです。
挨拶だけでは不十分です。
私だったら好きなゲームの話とかします。
スキーの話とかします。
仕事には感情がある。
それを「聞けない」経験から学びました。
私のように聞けないでいる方、勇気をだして雑談しましょう。
勇気を出して、少しだけ仕事の話を聞いてみましょう。
色々お話しましたが、一番大事なのは「勇気」です!